 其の一阡六百九拾七
其の一阡六百九拾七怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
 其の一阡六百九拾七
其の一阡六百九拾七
怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
| 撮影日 2022年11月28日 月曜日 アップ日 2025年09月04日 木曜日 |
||||||||||||||||||||||||
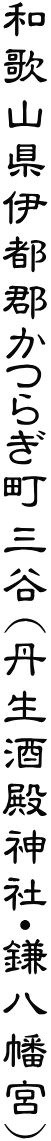 |
ワッカン~
資料として気になる街角 撮っておきや!(by UFO先生) 丹生酒殿神社(にうさかどのじんじゃ)は、和歌山県伊都郡かつらぎ町三谷に鎮座する神社。 高野山の麓、紀の川のほとりに位置し、境内社の鎌八幡宮は、 御神木に鎌を奉献(刺し)し願掛けをする信仰があり、 また高野参詣道の一つの「三谷坂」の起点であることでも知られている。 国の史跡「高野参詣道」を構成する資産として、丹生酒殿神社を含む「三谷坂」が指定されている。 世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」を構成する資産「高野参詣道」の一つとして、 丹生酒殿神社を含む「三谷坂」が登録されている。 (Wikipediaより) (※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
やはり持ってるものはUPして
資料的に残さねば… 気を抜いたらあきません~ 何時のが出てくるか判りまへんで! 袖擦り合うも他所の縁~ いつまで知った景色が在るのやら。。 頑張ってボチボチ更新中…^^;
|
|||||||||||||||||||||||