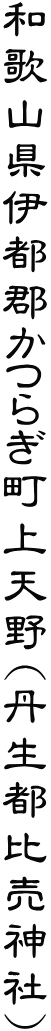大念仏一結衆宝篋印塔
大念仏寺(だいねんぶつじ)は、大阪府大阪市平野区にある融通念仏宗の総本山の寺院。
山号は大源山。本尊は十一尊天得如来(絵像)。
創建は大治2年(1127年)とされ、日本最初の念仏道場である。
「十一尊天得如来」とは融通念仏宗特有の呼称で、阿弥陀如来と十菩薩の絵像である。
(Wikipediaより)
※
|

祠
※石版
|

宝篋印塔
※ホンマですね~
|

外鳥居
四つ脚門
※案内板
|

奇麗な太鼓橋
※輪橋 - 太鼓橋。鏡池に掛かっている。
慶長年間(1596年 - 1615年)に淀殿の寄進で建立。
(Wikipediaより)
|

鏡池の中に善女龍王
先は中鳥居から楼門が見えます。
|

渡御復興記念碑
※和歌山県北東部、高野山北西の天野盆地に鎮座する。
空海が金剛峯寺を建立するにあたって丹生都比売神社が神領を寄進したと伝えられ、
古くより高野山と深い関係にある神社である。
神社背後の尾根上には高野山への表参道である高野山町石道(国の史跡、世界遺産)が通り、
丹生都比売神社は高野山への入り口にあたることから、高野山参拝前には
まず丹生都比売神社に参拝する習わしであったという。
丹生都比売神社自体も高野山からの影響を強く受け、
境内には多くの仏教系の遺跡・遺物が残る。和歌山県・奈良県を主とした各地では、
高野山の荘園に丹生都比売神社が勧請された関係で、
丹生都比売神社の分霊を祀る神社の分布が知られる。
(Wikipediaより)
|

楼門(重要文化財) - 室町時代の明応8年(1499年)の造営。
13世紀末の作という「絹本著色弘法大師丹生高野両明神像」
(金剛峯寺蔵)に描かれた境内図には、現在の楼門の位置に八脚門が描かれている。
現在の形式は三間一戸の入母屋造で、檜皮葺。
(Wikipediaより)
※社務所
丹生都比売神の性格については大きく分けて2説がある。
1つは水神とみるもので、その根拠として天野の地が紀の川の一水源地であること、
空海が丹生都比売神社から譲り受けたという神領は
有田川・貴志川・丹生川・鞆淵川の流域のほぼ全域を占めていたこと、
関係する丹生川上神社は水神信仰であること、東大寺のお水取りで水を送る
遠敷明神(おにゅうみょうじん;若狭彦神社)の存在、御田祭などの祭事における
性格等が挙げられる。
もう1つは、「丹」すなわち朱砂(辰砂:朱色の硫化水銀)の
採掘に携わる人々によって祀られたという説である。
『播磨国風土記』逸文にも「赤土」の記載が見えるほか、
全国にある「丹生」と名のつく土地・神社は、水銀の採掘に携わった氏族(丹生氏)と
深い関係にあることが明らかとなっている。
これらに対する一説として、丹生一族が水銀採掘で一大勢力を築いたが、
その枯渇に際して天野や三谷で帰農、丹生都比売神社も水神信仰に変化したとする説もある。
なお『丹生大明神告門』では、丹生都比売神を伊佐奈支命・伊佐奈美命の子とする。
また稚日女尊と同一神とする説もある。また、大国主神の御子神とする説もある。
(Wikipediaより)
|

楼門前の青銅製狛犬
阿
※吽
|

第一殿:丹生都比売大神(にうつひめのおおかみ)
通称「丹生明神」。古くより祀られていた神。
第二殿:高野御子大神(たかのみこのおおかみ)
通称「狩場明神」。高野山開創と関係する神。
第三殿:大食津比売大神(おおげつひめのおおかみ)
通称「気比明神」。承元2年(1208年)に氣比神宮(福井県敦賀市)からの勧請と伝える。
第四殿:市杵島比売大神(いちきしまひめのおおかみ)
通称「厳島明神」。第三殿と同年に厳島神社(広島県廿日市市)からの勧請と伝える。
(Wikipediaより)
※神社では国宝の銀銅蛭巻太刀拵を始めとする文化財のほか、
本殿および楼門などの社殿が国の重要文化財に指定されている。
また境内は国の史跡に指定されている。
これらのうち本殿、楼門および境内は、
ユネスコの世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部として登録されている。
また、弘法大師を高野山に導いたのが神様のお使いの
白黒2頭の犬であったという伝説から社にはご神犬がいる。
(Wikipediaより)
|

和歌山県北東部、高野山北西の天野盆地に鎮座する。
空海が金剛峯寺を建立するにあたって丹生都比売神社が神領を寄進したと伝えられ、
古くより高野山と深い関係にある神社である。
神社背後の尾根上には高野山への表参道である高野山町石道(国の史跡、世界遺産)が通り、
丹生都比売神社は高野山への入り口にあたることから、高野山参拝前には
まず丹生都比売神社に参拝する習わしであったという。
丹生都比売神社自体も高野山からの影響を強く受け、
境内には多くの仏教系の遺跡・遺物が残る。和歌山県・奈良県を主とした各地では、
高野山の荘園に丹生都比売神社が勧請された関係で、
丹生都比売神社の分霊を祀る神社の分布が知られる。
(Wikipediaより)
※
|

明治維新後、1873年(明治6年)に近代社格制度において県社に列し、
1924年(大正13年)に官幣大社に昇格した。1948年(昭和23年)に
神社本庁の別表神社に加列されている。
また、明治の神仏分離に伴い高野山から独立したが、今日に至るまで多くの僧侶が
丹生都比売神社に参拝しており、神前での読経も行われている。
第一殿(重要文化財) - 江戸時代の正徳5年(1715年)再建。
第二殿(重要文化財) - 室町時代の文明年間(1469年 - 1486年)再建。
第三殿(重要文化財) - 1901年(明治34年)再建。
第四殿(重要文化財) - 室町時代の文明元年(1469年)再建。
(Wikipediaより)
※綺麗に彩色されてます。
|

佐波神社(さわじんじゃ) - 明治時代に上天野地区の諸社を合祀したもの。
(Wikipediaより)
※心が洗われるような空間です。
|
 其の一阡六百壱拾八
其の一阡六百壱拾八 其の一阡六百壱拾八
其の一阡六百壱拾八