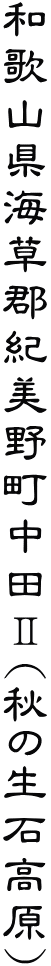今年も来ました~
※ビート(BEAT)は、本田技研工業が1991年5月から1996年にかけて
製造・販売していた軽自動車規格のオープンカー型ミッドシップスポーツカーである。
量産ミッドシップ車としては世界初のフルオープンモノコックボディを採用。
車体外観のデザインについてはホンダからの公式アナウンスはないものの、
ピニンファリーナの元デザイナーエンリコ・フミアは、
チェコスロバキア人デザイナーのパーヴェル・ハセックが担当したと語り、
自動車雑誌『スクーデリア』ではピニンファリーナ・ミトスをデザインした
ピエトロ・カマルデッラが担当したと記載している。
2010年5月9日には、ツインリンクもてぎで開催されたオーナーミーティングの
オーバルコースにおいて行われたパレードランに569台が参加した。
これはホンダの同一車種による世界最大のパレードランとなり、
ギネス・ワールド・レコーズに認定された。
販売から30年以上経過した2022年現在においても、
およそ1万5,000台あまりが現存しているという。
(Wikipediaより)
|

ススキ(芒、薄、学名∶Miscanthus sinensis)とは、イネ科ススキ属の植物。
尾花(おばな)や振袖草(ふりそでぐさ)ともいい秋の七草の一つ。
また茅(かや。「萱」とも書く)と呼ばれる有用植物の主要な一種。
野原に生息し、ごく普通に見られる多年生草本である。
※植物遷移の上から見れば、ススキ草原は草原としてはほぼ最後の段階に当たる。
ススキは株が大きくなるには時間がかかるので、初期の草原では姿が見られないが、
次第に背が高くなり、全体を覆うようになる。
ススキ草原を放置すれば、アカマツなどの先駆者(パイオニア)的な樹木が侵入して、
次第に森林へと変化していく。
茅場の場合、草刈りや火入れを定期的に行うことで、
ススキ草原の状態を維持していたものである。
かつては「茅」(かや)と呼ばれ、農家で茅葺(かやぶき)屋根の材料に用いたり、
家畜の餌として利用することが多かった。
そのため集落の近くに定期的に刈り入れをするススキ草原があり、
これを茅場(かやば)と呼んでいた。
(Wikipediaより)
|

天高く~
※
|

オオセンチコガネ(学名:Phelotrupes auratus)は、
コウチュウ目コガネムシ上科センチコガネ科に分類される昆虫の一種。
糞や腐肉、腐ったキノコを餌にするいわゆる糞虫の一群で、
金属光沢のある美しい体色をしている。
日本では北海道、本州、四国、九州に生息。
体長16-22㎜。通常は赤みを帯びた紫だが、地域変異が多く、
三重県などでは紫、赤、青の3つの体色を見ることができる。
活動期である4月から10月に、雑木林などの散策路を歩いているところを
目にすることが多い。春期と秋期に個体数を増す
(Wikipediaより)
※青色の個体
|

年に一度山焼きが行われるとか~
※
|

ノジギク(野路菊、学名 Chrysanthemum japonense)は、キク科キク属の多年生植物。
野菊の1種。植物学者の牧野富太郎が、1884年(明治17年)に高知県吾川村大崎で発見し、
1890年(明治23年)に命名した。
日本在来種で、本州(兵庫県以西)・四国・九州の瀬戸内海・太平洋沿岸近くの
山野などに自生する。
小菊の原種の一つ。イエギクの原種とも言われたが、
在来種で中国には自生していないことから、この考えは否定されている。
(Wikipediaより)
※後日11/13撮影
リンドウ(竜胆)とは、リンドウ科リンドウ属の多年生植物である。
別名はイヤミグサ。地方による別名は、イヤミグサ、ケロリグサなどがあり、
イヤミグサは、「胃病み草」の意味である。
古くはえやみぐさ(疫病草、瘧草)とも呼ばれた。
秋に咲く青紫の花は、キキョウとともによく知られている。
和名のリンドウは、中国植物名(漢名)の竜胆/龍胆(りゅうたん)の
音読みに由来し 、中国では代表的な苦味で古くから知られる熊胆(くまのい)よりも、
さらに苦いという意味で「竜胆」と名付けられたものである。
リンドウの全草は苦く、特に根は大変苦くて薬用になる。
かつては水田周辺の草地やため池の堤防などにリンドウやアキノキリンソウなどの草花が
たくさん自生していたが、それは農業との関係で定期的に草刈りがなされ、
草丈が低い状態に保たれていたためだった。
近年、そのような手入れのはいる場所が少なくなったため、リンドウをはじめ
これらの植物は見る機会が少なくなってしまい、
リンドウを探すことも難しくなってしまっている。
(Wikipediaより)
|

遠くユーラス有田川ウインドファームの風力発電施設が見えます。
※
|

NTT中継回線(NTTちゅうけいかいせん)は、
日本電信電話(NTT)およびその前身の事業体が所有・管理・運用している電気通信のための専用線。
アナログ伝送の時代は、NTTマイクロ波中継回線を使って番組を送受信する際に、
若干の画質の劣化が生じていた。
特に発局から遠ければ遠い局(例:東京→福岡)ほど、その差が出ていた。
2006年(平成18年)6月5日からデジタル回線へ移行したことにより、
民放キー局の番組もこの現象が無くなった。
現にNHKも、過去にアナログ回線を使用中に同じ現象が発生していたが、
現在は光ファイバーによるデジタル回線に移行され、全国で同じ画質および音声になっている。
(Wikipediaより)
麓からでも遠くても良く見えます。
※大石
|
 其の一阡六百壱拾七
其の一阡六百壱拾七 其の一阡六百壱拾七
其の一阡六百壱拾七