 其の一阡六百壱拾九
其の一阡六百壱拾九怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
 其の一阡六百壱拾九
其の一阡六百壱拾九
怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
| 撮影日 2023年03月22日 水曜日 アップ日 2025年01月06日 月曜日 |
|||||||||||||||||||||
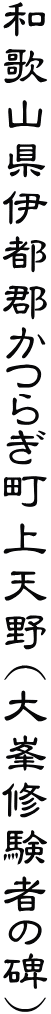 |
ワッカン~
資料として気になる街角 撮っておきや!(by UFO先生) 大峯修験者の碑(和歌山県指定有形文化財) - 境内東にある鎌倉時代から室町時代に 建てられた石造の五輪卒塔婆で4基ある。 高さは2.1メートルから3.6メートルあり、正応6年(1293年)、正安4年(1302年)、 文保3年(1319年)、延元元年(1336年)の刻銘がある。 修験行者の行事の模様をうかがわせるもので、和歌山県指定有形文化財に指定されている。 (Wikipediaより) (※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
やはり持ってるものはUPして
資料的に残さねば… 気を抜いたらあきません~ 何時のが出てくるか判りまへんで! 袖擦り合うも他所の縁~ いつまで知った景色が在るのやら。。 頑張ってボチボチ更新中…^^;
|
||||||||||||||||||||