 其の一阡六百九拾九
其の一阡六百九拾九怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
 其の一阡六百九拾九
其の一阡六百九拾九
怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
| 撮影日 2022年04月18日 月曜日 アップ日 2025年09月04日 木曜日 |
||||||||||||
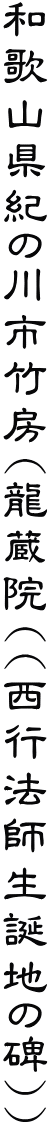 |
ワッカン~
資料として気になる街角 撮っておきや!(by UFO先生) 西行(さいぎょう、元永元年〈1118年〉- 建久元年2月16日〈1190年3月30日〉)は、 平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての日本の武士、僧侶、歌人。 西行法師と呼ばれ、俗名は佐藤 義清(さとう のりきよ)。 憲清、則清、範清とも記される。西行は号であり僧名は円位。 後に大本房、大宝房、大法房とも称す。 和歌は約2,300首が伝わる。 勅撰集では『詞花集』に初出(1首)。『千載集』に18首、『新古今集』に94首(入撰数第1位)を はじめとして二十一代集に計265首が入撰。 家集に『山家集』(六家集の一)、『山家心中集』(自撰)、『聞書集』。 その逸話や伝説を集めた説話集に『撰集抄』『西行物語』があり、 『撰集抄』については作者と注目される事もある。 (Wikipediaより) (※=マウスポインターを画像上に置いて下さい) やはり持ってるものはUPして
資料的に残さねば… 気を抜いたらあきません~ 何時のが出てくるか判りまへんで! 袖擦り合うも他所の縁~ いつまで知った景色が在るのやら。。 頑張ってボチボチ更新中…^^;
|
|||||||||||