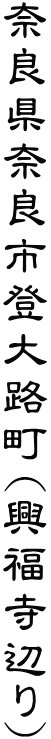興福寺
大湯屋
寺院の風呂場
寺院の風呂場として使われていた建物です。
奈良時代から設けられていたと考えられていますが、文献での初見は平安時代に降ります。
その後数回の被災・再建を繰り返し、現在の建物は室町時代に再建されたと考えられています。
詳細な年代は不明ですが、部材の特徴から、五重塔再建と同じ時期である応永33年(1426)頃と考えられています。
西面の屋根が入母屋である一方、東面の屋根は切妻であることから、大湯屋東側には何らかの建物があり、
大湯屋で沸かした湯を東側の建物に送って蒸し風呂にしていたか、
あるいは入浴・沐浴していたものと推測されています。
大湯屋内部は床を敷かず、地面に直接「鉄湯釜」を南北に2口据えます(鉄湯釜は奈良県指定文化財です)。
(興福寺HPより)
※興福寺本坊
平安時代頃から僧侶が生活し、学問にはげんだ建物
興福寺の寺務を執り行う場所です。
表門は天正年間(1573~1592)に建立された正面4.5m、側面2.6m、本瓦葺の四脚門(しきゃくもん)。
明治40年(1907)に菩提院(ぼだいいん)の北側築地の西方に構えられていた門を移築しました。
南客殿は同じ頃に増築された正面16.7m、側面10.0m、桟瓦葺(さんがわらぶき)の建物。
北客殿は嘉永7年(1854)に再建された正面20.0m、側面11.0m、桟瓦葺の建物で、
平安時代頃から僧侶が生活し、学問に励んだ東室(ひがしむろ)と呼ばれる東西に長い
僧房(そうぼう)の伝統を受け継いでいます。
(興福寺HPより)
|

人のいない柳茶屋周り~
早朝では無いのですがね。
※
|

興福寺境内
前には~
※五重塔屋根
|

東金堂
元正太上天皇の病気全快を願って造立
中金堂の東側にある金堂で、東金堂と呼ばれる西向きのお堂です。
神亀3年(726)聖武天皇が叔母の元正太上天皇の病気全快を願って建立されました。
創建当初は床や須弥壇などに緑色のタイル(緑釉塼/りょくゆうせん)が敷きつめられ、
薬師如来の東方瑠璃光浄土(とうほうるりこうじょうど)の世界が表されていたと言われています。
その後5度の被災・再建を繰り返し、現在の建物は室町時代の応永22年(1415)に再建されました。
前面を吹き放しとした寄棟造で、組物である三手先斗栱(みてさきときょう)が多用されるなど、
創建当初の奈良時代の雰囲気を色濃く伝えます。
堂内は室町時代に造立された本尊薬師如来坐像を中心に、
日光・月光菩薩(にっこう・がっこうぼさつ)立像、文殊菩薩(もんじゅぼさつ)坐像、
維摩居士(ゆいまこじ)坐像、十二神将立像、四天王立像などを安置しています。
(興福寺HPより)
※正面から~
七五三ですかね?
子供さんもマスクして~
|

中金堂
興福寺伽藍の中心になる最も重要な建物
中金堂は興福寺伽藍の中心になる最も重要な建物で、
寺伝では創建者を当時の日本の律令制度をまとめ、
藤原氏の栄光の基礎を築いた藤原不比等(ふひと)とします。
創建当初の中金堂の規模は当時の奈良朝寺院の中でも第1級でした。
当時は丈六釈迦如来像を中心に、薬王(やくおう)・薬上菩薩(やくじょうぼさつ)像と
十一面観音菩薩像を脇侍(わきじ)に従え、四天王像、さらに養老5年(721)に
橘三千代が夫不比等の1周忌に造立した弥勒浄土変の群像も安置されていたといわれています。
以後、創建より6回の焼失・再建を繰り返し、享保2年(1717)に焼失した後は
財政的な問題により再建が進まず、およそ100年経過した後に町屋の寄進により
規模を縮小した「仮堂」を文政2年(1819)に再建します。
しかし、あくまで仮設としての建立であったため、長期使用を想定しておらず、
材木には不向きなマツが使われるなどしたため、急速に老朽化が進みます。
そして、創建当時の様式で復元すべく、この仮堂は平成12年(2000)に解体しました。
その後、発掘調査を経て、平成22年(2010)の立柱式、平成26年(2014)の上棟式を経て、
平成30年(2018)に再建落慶を迎え復元されました。
(興福寺HPより)
※五重塔屋根
|

向こうに南円堂
ひと気が少ない~
鹿煎餅が無ければ鹿もいない。
※五重塔
|

三条通り東向き
※階段下りて~
|

登ります。
※
|

南円堂
立派な手水鉢
※
|

南円堂
内麻呂の冥福を願ってお建てになった八角円堂
南円堂は「西国三十三所」の第九番札所として人々の参拝が多い御堂です。
この堂は弘仁4年(813)藤原冬嗣(ふゆつぐ)が父の内麻呂(うちまろ)追善のために建立しました。
基壇築造の際には地神を鎮めるために、和同開珎や隆平永宝を撒きながら築き上げたことが
発掘調査で明らかにされました。
また鎮壇には弘法大師空海が大きく関わったことが伝えられています。
当時の興福寺は藤原氏の氏寺でしたが、藤原氏の中でも摂関家となる北家の力が強くなり、
北家の内麻呂・冬嗣親子ゆかりの南円堂は興福寺の中でも特殊な位置を占めました。
本尊である不空羂索観音菩薩(ふくうけんさくかんのんぼさつ)が身にまとう鹿皮(ろくひ)は、
神に仕える鹿への信仰、つまり氏神である春日社との関係により、藤原氏の強い信仰を集めました。
現在の建物は創建以来4度目のもので、寛保元年(1741)に立柱、寛政元年(1789)に再建されました。
再建には古代・中世の北円堂などの円堂を参考にしたと考えられていますが、
正面(東)には間口1間・奥行2間の「拝所」があり、唐破風(からはふ)が付いているなど、
江戸時代の細部様式もよく表しています
(興福寺HPより)
|

五重塔
古都奈良を象徴する塔。
釈迦の舎利をおさめる墓標
塔は釈尊の舎利(しゃり・遺骨のこと)を納める墓標であり、当時の仏教寺院においては権威の象徴でした。
塔を建てることは仏法の護持であり、大きな功徳とされます。
興福寺の五重塔は、天平2年(730)興福寺の創建者である藤原不比等(ふひと)の娘
光明皇后の発願で建立されました。
その後5回の焼失・再建を経て、現在の塔は応永33年(1426)頃に再建されました。
日本で2番目に高い塔で、古都奈良を象徴する塔です。
創建当初の位置に再建され、三手先斗栱(みてさきときょう)と呼ばれる組物を用いるなど
奈良時代の特徴を随所に残していますが、中世的で豪快な手法も大胆に取り入れています。
創建当初の高さは約45mで、各層には水晶の小塔と無垢浄光陀羅尼経(むくじょうこうだらにきょう)が、
また初層には四天柱の各方向、東に薬師浄土変、南に釈迦浄土変、西に阿弥陀浄土変、
北に弥勒浄土変が安置されていたと言われ、当時日本で最も高い塔でした。
現在もその伝統を受け継ぐ薬師三尊像、釈迦三尊像、阿弥陀三尊像、
弥勒三尊像(いずれも室町時代作)が初層のそれぞれ須弥壇四方に安置されます。
(興福寺HPより)
※絵に成りますね。
|

|
 其の一阡六百八拾一
其の一阡六百八拾一 其の一阡六百八拾一
其の一阡六百八拾一