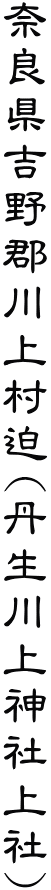R169で熊野に作業に行く途中に
大滝ダム横に標識が有り気に成ってました。
※手水鉢
|

幟
|

創祀1350年だそうです。
※紅葉の時期
|

拝殿舎正面
現在の本殿は三間社流造銅板葺。
旧境内地が大滝ダムの建設に伴い水没することになったため、
伊勢神宮旧社殿の古材を用い平成10年に造営された。
なお、旧社殿は大正6年(1917年)の造築にかかるもので、飛鳥坐神社(高市郡明日香村)に移築され、
同神社の本殿などとなっている。
(Wikipediaより)
※扁額
簡素な造で木彫は見られない
|

御神木 杉樹幹
※
|

明治初年までは高龗神社という小規模な祠で、その由緒も不詳であるが、
大滝ダム建設に伴う境内の発掘調査により宮の平遺跡が発見され、
本殿跡の真下から平安時代後半(11世紀末)以前に遡る自然石を敷き並べた祭壇跡が出土し、
また付近からは、縄文時代中期末から後期初め(約4000年前)にかけての祭祀遺跡と見られる、
立石を伴う環状配石遺構が出土したため、途中奈良・古墳時代にかけての断絶が認められるものの、
当神社の祭祀空間としての機能は縄文時代にまで遡る可能性が出てきた。
(Wikipediaより)
※紅葉の季節
|

白屋岳(1177.0m)が正面に
※本宮遥拝所
|

大滝ダム(おおたき龍神湖)眼下に~
大滝ダム(おおたきダム)は、奈良県吉野郡川上村、
一級河川・紀の川本流上流部に建設されたダムである。
国土交通省近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所が
管理する高さ100メートルの重力式コンクリートダム。
伊勢湾台風による紀の川の大水害を機に紀の川の治水と、上流の大迫ダムなどと共に
奈良市・和歌山市などへの利水、および出力1万500キロワットの水力発電を目的とした
特定多目的ダム法に基づく特定多目的ダムである。
計画以来地元の反対運動が激しく補償交渉が極めて長期化したほか、完成直前に貯水池斜面が
地すべりを起こして対策に時間が掛かるなど完成までに50年の歳月を費やした
日本の長期化ダム事業の代表格。
2004年(平成16年)に利水目的の暫定供用を開始し、
2012年(平成24年)6月に治水目的の供用が開始された。
ダムによって形成された人造湖は、公募によりおおたき龍神湖と名付けられた。
(Wikipediaより)
※
|

地域振興事業としては国道169号の整備を始め国道に沿った川上村官庁街の整備、
村営ホテルや温泉宿泊施設の整備を行った。
更に二十二社の一つとして平安時代中期に創建された由緒ある丹生川上神社上社が水没する事もあり、
1998年(平成10年)に高台に遷座する作業が行われた。
ところが移転後の跡地から遺跡が発見され、3年間に亘る発掘調査が行われた。
この宮の平遺跡は縄文時代早期の大規模集落跡であり、この地は古代から人の住まう土地である事も判明した。
日本の長期化ダム事業の代表例として、長い年月を掛けた補償は終了し
1996年よりダム本体工事に取り掛かることとなったが、ここに漕ぎ着けるまで実に34年の月日が過ぎ去っていた。
東の八ッ場、西の大滝とも~
(Wikipediaより)
※
|

明治6年(1873年)に郷社に列したが、当時の官幣大社丹生川上神社(現在の下社)少宮司江藤正澄が、
下社の鎮座地は寛平7年(895年)の太政官符(『類聚三代格』所収)に記す
丹生川上神社の四至境域に合致しないことを指摘して当神社を式内丹生川上神社に比定し、
翌明治7年には当神社を下社所轄の神社とするとともに、下社を「口の宮」、当神社を「奥の宮」と称した。
その後江藤説が認められて、明治29年(1896年)に「口の宮」を「丹生川上下社」、
当神社を「同上社」と改称し、2社を合わせて「官幣大社丹生川上神社」となった。
(Wikipediaより)
※
|

1163mの嶺も~
※
|
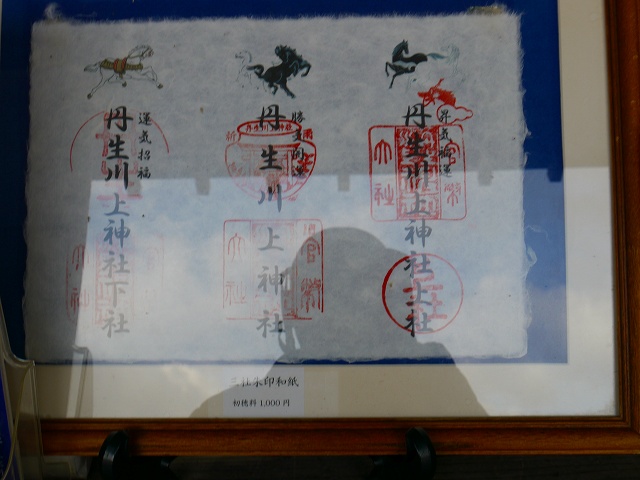
大正(1915)4年 、現・中社のある東吉野村出身の森口奈良吉が『丹生川上神社考』を著して、
「蟻通神社(現丹生川上神社・中社)=丹生川上社説」を唱え、これが受け入れられたため、
同11年(1922年)10月12日内務省告示で「郷社丹生川上神社、奈良県吉野郡小川村鎮座、祭神罔象女神。
右官幣大社丹生川上神社中社ト定メラルル旨被仰出」とされ、上社・下社は中社に包括される形で、
改めて3社を合わせて「官幣大社丹生川上神社」とされた。その際、上社の祭神は罔象女神から
郷社時代と同じ高龗神に再び戻された。
第二次大戦後の昭和27年(1952年)に独立し、現在は神社本庁に属して、その別表神社とされている。
(Wikipediaより)
※
|

|
 其の一阡六百六拾三
其の一阡六百六拾三 其の一阡六百六拾三
其の一阡六百六拾三