 其の一阡六百五拾五
其の一阡六百五拾五怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
 其の一阡六百五拾五
其の一阡六百五拾五
怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
| 撮影日 2024年10月09日 水曜日 アップ日 2025年02月08日 土曜日 |
||||||||||||||||||
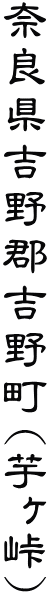 |
ワッカン~
資料として気になる街角 撮っておきや!(by UFO先生) 芋ヶ峠(いもがとうげ)は、奈良県吉野郡吉野町、
大淀町と高市郡明日香村、高取町との町村境付近にある峠。 現在の県道が通る峠付近では、この4つの自治体の町村境が接続する。 峠道は吉野町と明日香村とを結ぶものだが、北斜面を走る県道は峠から 明日香村栢森までの大半は高取町内を通っている。 なお、県道が付けられる以前の旧峠道は東よりの小峠を越え、尾 根を登るため全て明日香村内を通り、旧峠も吉野町と明日香村の町村境にある(古道芋ヶ峠)。 標高497m。芋峠、今峠とも。また近世には疱瘡峠と書いて「いもとうげ」と呼んだ。 古代において都のあった飛鳥と、離宮のあった吉野とを最短で結ぶ道として開かれ 天武天皇、持統天皇などの天皇の吉野行幸では、 この峠道が使われたのではないかと考えられている。 また藤原道長が吉野に入るのに利用した。中世以降は吉野山、大峯山への参詣道として 盛んに用いられたが、大和国名所旧蹟巡覧をする旅人は芋ヶ峠よりも多武峰・談山神社から入る 龍在峠をよく利用し、芋ヶ峠は国中(奈良盆地)から吉野へと運ばれる 物資が多く行き交っていたという。 なお、芋ヶ峠の道は国中側では岡寺を経て八木まで通じており、これらを総じて吉野側では 街道(または岡寺街道)」、国中側では「芋峠越吉野街道」と呼ばれた。 (Wikipediaより)
やはり持ってるものはUPして
資料的に残さねば… 気を抜いたらあきません~ 何時のが出てくるか判りまへんで! 袖擦り合うも他所の縁~ いつまで知った景色が在るのやら。。 頑張ってボチボチ更新中…^^;
|
|||||||||||||||||