 其の一阡六百五拾
其の一阡六百五拾怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
 其の一阡六百五拾
其の一阡六百五拾
怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
| 撮影日 2024年03月15日 金曜日 アップ日 2025年02月08日 土曜日 |
||||||||||||
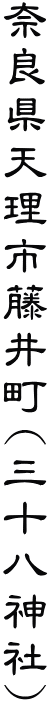 |
ワッカン~
資料として気になる街角 撮っておきや!(by UFO先生) 二宮金次郎像 各地の小学校などに多く建てられた、薪を背負いながら本を読んで歩く姿 (「負薪読書図」と呼ばれる)に関する記述は、 明治14年(1881年)発行の『報徳記』が初出である。 そこには「大学の書を懐にして、途中歩みなから是を誦し、少も怠らず。」とある。 この「書を懐にして」を、「懐中」か「胸の前で持って」と 解釈するかは判断に迷うところだが、金治郎像では後者で解釈されている。 ただし先述のように『報徳記』の尊徳幼少期の記述は信憑性が薄く、 このような姿で実際に歩いていたという事実があったかは疑問が残る。 『報徳記』を基にした幸田露伴著の『二宮尊徳翁』(1891年10月)の挿絵(小林永興画)で、 はじめて「負薪読書図」の挿絵が使われた。 ただし、これ以前から既にこの図様に近い少年像は存在していた。 金治郎の肖像画のルーツは中国の「朱買臣図」にあり、これが狩野派に伝統的な画題として 代々伝わり、その末裔の永興もこれを参考にしたと想定される。 確認されている最初のこの姿の像は、明治43年(1910年)に岡崎雪聲が 東京彫工会に出品した『二宮金次郎像』である。 (Wikipediaより) やはり持ってるものはUPして
資料的に残さねば… 気を抜いたらあきません~ 何時のが出てくるか判りまへんで! 袖擦り合うも他所の縁~ いつまで知った景色が在るのやら。。 頑張ってボチボチ更新中…^^;
|
|||||||||||