 其の一阡六百四拾四
其の一阡六百四拾四怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
 其の一阡六百四拾四
其の一阡六百四拾四
怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
| 撮影日 2024年12月23日 月曜日 アップ日 2025年01月29日 水曜日 |
||||||||||||||||||||||||||
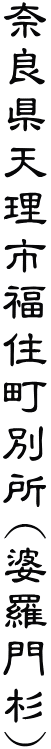 |
ワッカン~
資料として気になる街角 撮っておきや!(by UFO先生) 天理市福住町に所在する下之坊(しものぼう)はもと普光院永照寺といい、長谷寺の末寺です。 この下之坊に上る参道石段の南北両側に、あたかも山門のようにそびえる 2本のスギの巨樹があります。 南北のスギはいずれも樹勢が盛んで、根張りの範囲は下之坊の境内全体に及んでいます。 樹齢は700 年から800 年とされていますが、詳細は明らかになっていません。 下之坊の大スギは県下でも有数のスギの巨樹であり、 なかでも北側のスギの形状は特異な生態を示す事例として学術的価値が高いものです。 また、下之坊の大スギは通称「婆羅門杉(ばらもんすぎ)」とも呼ばれ、 地域の人々によって今も大切に守り継がれています。 (天理市HPより) (※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
やはり持ってるものはUPして
資料的に残さねば… 気を抜いたらあきません~ 何時のが出てくるか判りまへんで! 袖擦り合うも他所の縁~ いつまで知った景色が在るのやら。。 頑張ってボチボチ更新中…^^;
|
|||||||||||||||||||||||||