 其の一阡六百参拾九
其の一阡六百参拾九怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
 其の一阡六百参拾九
其の一阡六百参拾九
怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
| 撮影日 2021年10月27日 水曜日 アップ日 2025年01月26日 日曜日 |
||||||||||||
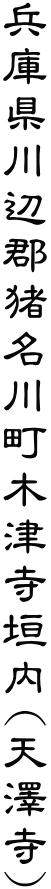 |
ワッカン~
資料として気になる街角 撮っておきや!(by UFO先生) 天澤寺(てんたくじ) 奈良時代に高僧行基が開いた、楊津院(やないづのいん)の後身と伝えられています。 東大寺の大仏建立等につくした行基は、伊丹の昆陽寺をはじめとした 四十九院を建てていますが、楊津院もその一つです。 境内の石灯籠には応永10年(1403)銘が入っています。 この時期の石灯籠としては県下でも稀な例であるため兵庫県指定文化財になっています。 (猪名川町HPより) (※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
やはり持ってるものはUPして
資料的に残さねば… 気を抜いたらあきません~ 何時のが出てくるか判りまへんで! 袖擦り合うも他所の縁~ いつまで知った景色が在るのやら。。 頑張ってボチボチ更新中…^^;
|
|||||||||||