 其の一阡六百参拾一
其の一阡六百参拾一怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
 其の一阡六百参拾一
其の一阡六百参拾一
怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
| 撮影日 2021年08月22日 日曜日 アップ日 2025年01月17日 金曜日 |
||||||||||||
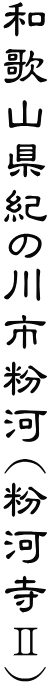 |
ワッカン~
資料として気になる街角 撮っておきや!(by UFO先生) 草創時この方、粉河寺は多くの人達の信仰をうけて繁栄し、鎌倉時代には七堂伽藍、 五百五十ヶ坊、東西南北各々四キロ余の広大な境内地と寺領四万余石を有していたが、 天正十三年(1585)豊臣秀吉の兵乱に遭遇し、偉容を誇った堂塔伽藍と多くの寺宝を焼失した。 その後、紀州徳川家の庇護と信徒の寄進によって、 江戸時代中期から後期に現存の諸堂が完成した。 (粉河寺HPより) (※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
やはり持ってるものはUPして
資料的に残さねば… 気を抜いたらあきません~ 何時のが出てくるか判りまへんで! 袖擦り合うも他所の縁~ いつまで知った景色が在るのやら。。 頑張ってボチボチ更新中…^^;
|
|||||||||||