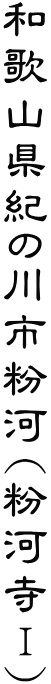大門
規模の大きい三間楼門で、和歌山県では、
高野山・根来寺に次ぐ威容を誇る。
宝永四年(一七〇六)総欅造り。
金剛力士は仏師春日の作と云われ、
尊像の用材は桂の巨木。
(粉河寺HPより)
※献灯
立派な手工業品
|

大門の立派な造形の仁王像
阿
※吽
|

石畳を先へ~
石畳好きですねん!
※新型コロナの影響で
参詣客が少なかったです。
|

左の道標で中津川路…
西側に流れている川が中津川です。
右の道標
左 かつらぎ山上 役行者道
※右 粉河寺
現代の案内図
|

役行者道~
※見返って~
|

粉河寺本堂に向かって~
※本坊の立派な門
|

瓦の造作が見事です。
菊花紋
|

童男堂
紅白の鮮やかな仏堂が左手に見える。
延宝7年(1679年)に建立された童男堂である。
寺伝では、紀州藩の出である八代将軍吉宗の寄進とされ、
昭和53年の半解体修理で往時の姿を取り戻した。
本尊は当山千手千眼観世音菩薩の化身である童男大士(童男行者)を
まつり(写真下)、毎年12月18日の童男会の法要に併せて開帳される。
(粉河寺HPより)
※廊下の柱の擬宝珠
蓮の花と葉ですね。
|

瓦が綺麗です。
飾り瓦に鯱や龍が見られます。
※
|

堂内
※天井
|

仏足石
※
|

表面
※裏面
|

出現池
※童男大士石像
|

三角堂
下は出現池
祈願が成就したら鯉を放すとか~
|

石標
※此処から覗くと~
|

馬蹄石
|

念仏堂(光明殿)
江戸時代後期建立。総欅造。
※
|

木鼻獅子
阿
※吽
|

鉄髭龍
※立体的です。
|

破風付きの
立派な建物
※飾り瓦は菊花
|

阿弥陀如来坐像(紀の川市指定有形文化財)露座仏。
文久2年(1862年)作。
紀州藩第8代藩主徳川重倫らの寄進。
※バックの白壁の中に
御池坊庭園(紀の川市指定有形文化財)が在るとか~
|

舟のような植栽
※立派な角刈り~
|

説明は無い建物ですが~
※瓦屋根が残念!
|

大師堂
※脇の行者堂に続く石畳道
|

何処に有ったのか?
自然石道標
いせ、こうや、まきのお
※四角柱の道標
往来安全
若山、紀三井寺
|

右 粉河寺、根来、大阪道
※左 いせ、こうや、まきのう道
|

この石橋は?
※実学社猛山学校跡
明治政府は近代国家として国家財政を確立し、
土地制度および土地課税の変革をするため、
明治6年(1873)に「地租改正条例」を制定したが、
地価の算定などに問題があり農民の負担が大きかった。
明治9年(1876)、児玉仲児
『嘉永2年(1849)~明治42年(1909)紀の川市 生まれ自由民権運動の牽引者』は
画一的で不合理な算定に異議を唱え、建白書を県に提出。
趣旨に賛同した粉河村の戸長や有力者たちも同様の願書を提出し、
ついには粉河騒動といわれる数千人の請願行動に拡大、県が軍隊の出動を要請するに至った。
仲児はこの一連の反対運動を契機に、近代的な人権の確立を目指して人々の生活と
意識を変えていこうとする自由民権運動を展開していく。
仲児らの呼びかけで「実学社」が結成され、国会設立の請願を行うとともに、
新時代を担う人材育成のため、猛山学舎(後に猛山学校)を開校。
歴史、法律、作文、算数やイギリスなどの自由思想の講義を行った。
(和歌山県ふるさとアーカイブHPより)
|

大畑 才蔵(おおはた さいぞう、1642年(寛永19年)- 1720年(享保5年))は、
日本の農業土木技術者。江戸時代、紀州藩で、水利事業に大きな貢献をし、
小田井用水路、および藤崎井用水路の紀の川から引水した大規模かんがい用水・疏水工事を
行った人物として知られる。
諱(いみな)を勝善という。戒名は、『浄岸慈入居士』。
(Wikipediaより)
※
|

小田井用水路は、2017年10月10日メキシコ・メキシコシティーで開催された
第68回国際かんがい排水委員会国際執行理事会において世界かんがい施設遺産への
登録が決定された。
(Wikipediaより)
※小田井・藤崎井
両用水銘がみえます。
|

有本芳水碑
有本 芳水(ありもと ほうすい、
1886年(明治19年)3月3日 - 1976年(昭和51年)1月21日)は、
日本の詩人・歌人である。
本名歓之助。兵庫県飾西郡津田村(現・姫路市)に生まれる。
(Wikipediaより)
※
|

この水盤は?
安永4年(1775)粉河鋳物師
蜂屋薩摩掾五代目源正勝の作品とか。
|

粉河寺の復興とともに江戸時代に盛況を博した粉河鋳物は、粉河門前町に居住した鋳物師が製作。
仏像・梵鐘・半鐘・鰐口、燭台・銅花瓶など仏具類を中心に多岐にわたります。
慶長10年(1605)に製作された粉河寺大門橋の高欄宝珠は、粉河鋳物の初めの
作品と考えられており、県指定文化財になっています。
鋳物師が江戸に住んだこともあり、粉河鋳物は近隣のまちだけでなく、
関東や東北地方にも作品が残ります。
作品からその当時活躍した鋳物師の名前や技術の高さなど、様々な歴史を知ることができます。
(紀の川市歴史資料館企画展「粉河鋳物展―粉河鋳物師の匠の世界―」より)
※我が亡父も鋳物師でした。
|
 其の一阡六百参拾
其の一阡六百参拾 其の一阡六百参拾
其の一阡六百参拾