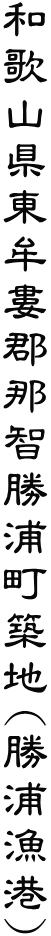R42から脇道にそれて~
※
|

築地西交差点
※タイムス駐車場に入れます~
|

海沿いは旅館が多いのですね。
※勝浦湾
|

駐車場は向かい側に有ります~
※
|

フォークリフトに積んでいるのは~
※マグロなんですわ!
|

大きな製氷工場
※漁港風景~
|

波止場なんですね。
※
|

マグロたちが~
水揚げされて~
※
|

喫水の高いマグロ船~
※日常風景~
|

※
|

勝浦湾
※日本全国から漁船が集まっています。
|

可愛い亀外装の定期船
※
|

港風景~
※
|

※
|

紀の松島方向~
※若い人たちの中には
外国の言葉も飛び交って~
|

埋立地ですね
奇麗な港湾風景
※
|

この物体は?
※メカジキ(目梶木、眼梶木、学名 Xiphias gladius )は、
バショウカジキ目メカジキ科に分類されるカジキの一種である。
カジキ類の中でも最大級で、食用に漁獲される。
メカジキ科唯一の現生種であり、メカジキ属唯一の種である。
(Wikipediaより)
|

ビンナガ(鬢長、学名:Thunnus alalunga)は、スズキ目・サバ科に分類される魚の一種。
全世界の熱帯・温帯海域に分布する小型のマグロで、缶詰などに用いられる重要な食用魚である。
「マグロ」をつけてビンナガマグロ、または「長」を音読みしビンチョウ、ビンチョウマグロとも呼ばれる。
異名としてトンボマグロ、シビマグロ、他の地方名としてビナガ(宮城南部)、ビンチョ(宮城北部)、
カンタロウ、カンタ(三重)、トンボ、トンボシビ(関西・高知)などもある。
(Wikipediaより)
※
|

遠洋クロマグロ船
※
|

数十年前の勝浦湾に海中井戸がありました。
海岸から120m離れた海中で真水が湧き出ていたのです。
明治27年(1894)頃に勝浦の岸庄次郎氏が
この湧水の周囲に井戸枠を作って海水の混入を防いで、
それ以降、勝浦港に入港する船舶はこの海中井戸の清水で給水をしたそうです。
この海中井戸について次のような伝説があります。
むかし、文覚上人が那智の滝で荒行することを思い立って、
船で熊野灘をさしかかったとき、一頭の鯨がシャチに追われているのを見た。
かわいそうに思った文覚上人は念仏を唱えながら、
持っていた杖を投げてシャチを追い払った。
そして陸に上がると、子供たちがモグラをいじめているのを見て、子供たちに金をやり、モグラを逃がしてやった。
さて那智の滝まで来ると、滝壺が深くて中に入れない。
すると、足下からモグラが出て来て「ご恩返しに穴を掘って滝壺の水を減らしましょう」といい、
何千何万というモグラが集まってトンネルを掘り出した。
すると、海では鯨が集まって、トンネルに流れ込む水を吸い込んでは背中から噴き出して、
モグラたちが溺れないように手助けをした。
それで、滝壺の水は見る見るうちに減り、文覚上人は喜んで滝壺に入り、荒行をすることができた。
(熊野謎解きめぐりHPより)
※昔の写真展
|

延縄漁による
生マグロ水揚げ量日本一
延縄(はえなわ)は、漁業に使われる漁具の一種。
1本の幹縄に多数の枝縄(これを延縄と呼ぶ)をつけ、
枝縄の先端に釣り針をつけた構成となっている。
また延縄を用いた漁法を「延縄漁」と呼ぶ。
延縄漁は古くから用いられた漁法で、延縄を漁場に仕掛けた後、
しばらく放置して再び延縄を回収して収獲を得る。
網を使った漁法に比べて、時間が掛かり漁師の作業量が多く効率の点で劣る。
狙った魚だけを獲得するのが比較的可能であるため
漁業資源に対して優しい漁法だという利点を主張する声がある一方で、
ウミガメや海鳥が針にかかり死亡するケースが多いためにこの漁法を問題視する声もある。
(Wikipediaより)
※クロマグロ
成魚は全長3 m・体重400 kgを超え、日本沿岸で漁獲されるマグロ類としては最大種である。
体型は太短い紡錘形で、横断面は上下方向にわずかに長い楕円形をしている。
体表は小さな鱗があるが、目の後ろ・胸鰭周辺・側線部は大きな硬い鱗で覆われ、「胸甲部」と呼ばれる。
体色は背中側が濃紺、体側から腹部にかけてが銀灰色をしている。
背鰭は二つとも灰色だが、第二背鰭先端とその後に続く小離鰭(しょうりき)は黄色を帯びる。
尻鰭とその後に続く小離鰭は銀白色をしている。
また、幼魚期は体側に白い斑点と横しま模様が10-20条並んでおり、
幼魚の地方名「ヨコワ」はここに由来する。
(Wikipediaより)
|

熊野参詣道(大辺路)
駿田峠方面~
※
|
 其の一阡六百壱拾三
其の一阡六百壱拾三 其の一阡六百壱拾三
其の一阡六百壱拾三