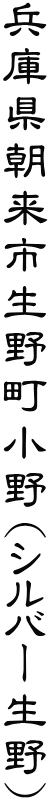代官屋敷門
江戸時代に入ると生野奉行が置かれ、第三代将軍・家光の頃に最盛期を迎え、
月産150貫(約562kg)の銀を産出した。
宝永2年(1705年)には、「御所務山(ごしょむやま)」という最上級の鉱山に指定されている。
慶安年間(1648年 - 1652年)頃より銀産出が衰退し、享保元年(1716年)には
生野奉行は生野代官と改称した。江戸中期には銀に換わり、銅や錫の産出が激増している。
(Wikipediaより)
※由来記
|

坑内トロッコ
※江戸期の坑道内模型
蟻の巣のように…
|

山神宮分社と見石
江戸末期に手掘りで掘られた坑道とか~
マネキン人形(GINZAN BOYZ)があちこちに…
※
|

内部
金山彦を祀る
※近畿地方でも最大規模のヒカゲツツジの群生地
ヒカゲツツジ(日陰躑躅、学名:Rhododendron keiskei Miq.)は、
ツツジ科ツツジ属に分類される常緑低木の1種。
和名のヒカゲツツジは日陰に多く生えることに由来するが、日陰だけに生えている訳ではない。
別名のサワテラシは河岸の岩場に生えることに由来する。
シャクナゲに近い形態をしており、ツツジの名が付くが実際は有鱗片シャクナゲに分類されるべきものである。
蒴果は長さ8-13 ㎜の円柱形。幹は灰褐色-灰白色。
濃い緑色の長楕円形または披針形の長さが4-8 ㎝の薄い革質の葉を枝先に互生させ、
枝先に集まって付く。裏側は淡褐色で腺状鱗毛が密生する。
先が細り、先端に腺状突起を有する。若枝や葉柄にも鱗状毛があり、長毛も混じる。
日本では4-5月頃に枝先にクリーム色ないしは淡黄緑色の花を2-4個集まって咲かせる。
花冠は径3-4 ㎝で5中裂し、雄しべは10本、外面に腺状鱗毛を散生させる。
花糸の下部には白い軟毛を散生させ、花柄は長さ1-1.5 ㎜。
庭木や鉢植えとして利用されている。
(Wikipediaより)
|

生野銀山 観音岩
※不動の滝
此処にもマネキン人形が~
|

金香瀬坑道入口
全長約1000m
年間を通じて約13度の気温
約40分の貴重な体験
1200年の歴史ロマンの史跡とか~
※
|

江戸期の狸堀
有望そうな地層を支えもなしに
横穴を掘り進んだ跡とか~
※
|

サンドスライム充填採掘法
戦後の技術とか~
※スラッシャー
此処にも…
|

掘った後に埋め戻す~
※1.5t蓄電池機関車
|

1t 鉱車大漁大漁!!
※
|

賑やかな現場だったんでしょうね~
※五枚合掌支柱組
木製柱
|

トロッコが通った坑道~
※
|

電気発破
※此処にも~
|

此処にも~
※掘った跡
|

先へ~
※
|

堀跡
光が当たれば苔生します。
※
|

ローダー
※
色んな機械が在ったんですね。
|

馬蹄形鋼枠二枚合掌
坑内風景は前に~
01 02 03 04
※
|

横向きさく孔用ドリフター
※鉱脈~
|

地下水が~
※
|

巻揚機
※大きなワイヤーリール
|

昭和4年のIHI製
※なんで鉱脈が分かるんでしょうね?
|

トロッコ列車
l※人車
|

坑内断面図
※
|

江戸期の石臼
※作業風景~
サザエの殻に魚油を入れての明り取り
暗かったでしょうね。
|

手掘りで
これだけの広場をつくろうと思えば
時間がとてもかかるでしょうね~
※出方相改・定番下代
|

トロッコ軌道跡
※外は明るい~
|

昭和48年(1973年)3月22日、資源減少による鉱石の品質の悪化、
坑道延長が長くなり採掘コストが増加し、山ハネなどにより採掘が
危険となったことから閉山し1200年の歴史に幕を閉じた。
坑道の総延長は350km以上、深さは880mの深部にまで達している。
なお、閉山後は三菱鉱業(現・三菱マテリアル)が引き続き
銀山周辺に生野事業所を設置し、現在も生野の主要産業となっている。
閉山後の1974年に、史跡 生野銀山
(三菱マテリアルと朝来市が出資する第三セクター会社、シルバー生野が管理・運営)
という名称でテーマパークを開業した。
のみの跡も生々しい坑道巡りのほか、鉱山資料館には
「和田コレクション(和田維四郎)」をはじめとした多数の貴重な鉱物が展示されていましたが、
2023年2月現在では埼玉県大宮の三菱マテリアルへ移動している。
2007年に近代化産業遺産、および日本の地質百選に選定された。
(Wikipediaより)
※明治元年(1868年)から日本初の政府直轄運営鉱山となり、鉱山長・朝倉盛明を筆頭として、
お雇いフランス人技師長ジャン・フランシスク・コワニエらの助力を得て、
先進技術を導入し近代化が進められた。
明治22年(1889年)から宮内省所管の皇室財産となり、
明治29年(1896年)に三菱合資会社に払下げられ、国内有数の鉱山となった。
明治から大正にかけての生野銀山を舞台とする小説に、
玉岡かおるの『銀のみち一条』(新潮社 2008年)がある。
(Wikipediaより) |

菊の御門入りの門柱
※
|

※
|

フランス人が門柱制作の責任者
※
|

明治初期にフランス人技師
ジャン・フランソア・コァニェが選鉱所建屋の一部の赤煉瓦
生野で焼かれたとか~
※煉瓦の接着には漆喰が使われたとか~
|
 其の一阡六百三
其の一阡六百三 其の一阡六百三
其の一阡六百三